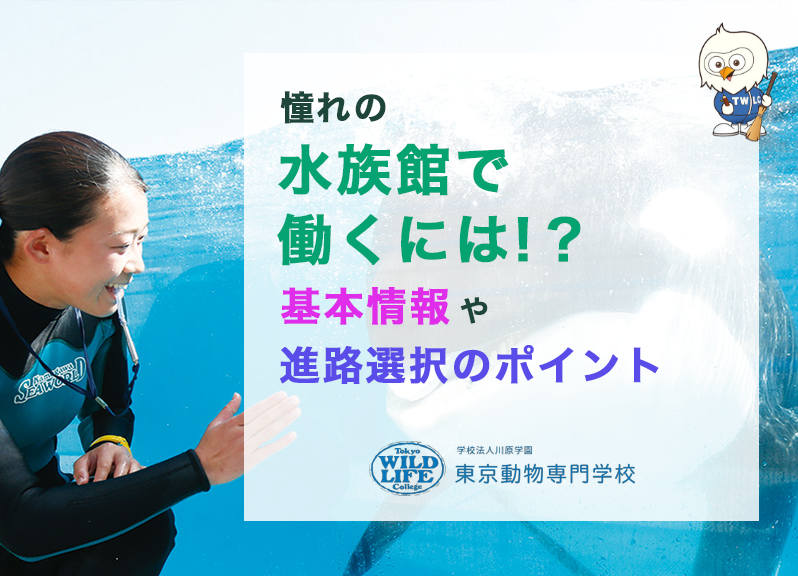
こんにちは!東京動物専門学校 学生課の川原祥孝です。
前回までは動物園やサファリパークで働く飼育員について解説してきましたが、今回からは水族館に焦点を当て、水族館で働くにはどうしたらいいのか、知っておきたい「基本情報」から夢の実現に向けての「進路選択のポイント」について、解説していきます。ぜひ進路の参考にしてもらえたらと思っています。
それでは始めていきましょう。
【目次】
・水族館で働くとは??
・憧れの水族館で働くにはどんな進路がある?
・学校の選び方
・夢に向け今からできる準備
水族館といえば、シャチやイルカ、アシカ、アザラシ、オットセイ、ペンギン、その他爬虫類や魚類、原生動物などの水に生きる動物たちが集まる場所。
ひとたび足を踏み入れれば、その水中を優雅に泳ぎ抜ける美しさや立ち居振る舞い、鮮やかな色、パフォーマンスショーでの人間とのコミュニケーションなどに魅せられ、年間パスポートを購入して何度も訪れる人がたくさんいるのではないでしょうか。そうした中、
「そんな水族館の動物たちに囲まれて働きたい!」
「ショートレーナーになって感動を届けたい!」
そんな憧れを抱く高校生も多いのではないかと思います。
では、水族館の仕事は実際にはどんな内容で、水族館で働くにはどのような道を進めばいいのでしょうか。今回は、幅広い動物種を飼育する水族館の仕事の中で、特に東京動物専門学校の卒業生が担当する海生哺乳類や鳥類を飼育する飼育員に焦点をあてながら見ていきたいと思います。
水族館で働くとは??
水族館の主な職種と仕事内容
水族館で働くスタッフには様々な職種があります。中心となるのは、動物たちの日々の生活を支える飼育スタッフ(水族館飼育員)です。水族館飼育員の仕事内容
水族館飼育員は、イルカやアシカなどの海獣類やペンギンなどの鳥類、魚類など、水族館で飼育展示される水棲生物のお世話をするのが主な仕事です。お世話といっても色々あります。例えば、
- 餌やり
- ボディチェックなどによる健康状態の確認
- 担当動物の展示スペースの整備
- 動物舎(展示場裏の控室)の清掃などが挙げられます。
例えばエサやりは、ただエサをあげればいいかというと、そうではありません。動物種ごとに食性(どんなものを食べるか)が異なりますから、それらに合わせて調理・準備します。
またあげる際は、餌の食べ残しによる水質悪化が起こらないよう、残さず食べてもらうよう注意しながらあげていきますし、群で飼育している動物の場合は、食べそびれる個体が出ないよう、全ての個体に行き渡るよう工夫します。
水族館と聞くと、イルカやアシカショーのショーパフォーマンスや動物たちのお食事タイムを思い浮かべる人も多いと思いますが、それらのイベントを担っているのも、実は水族館飼育員です。
水槽を清掃する、ショーのためのトレーニング、パフォーマンスを行う、水中で餌やりイベントを行う、、、。仕事で「水に潜って水中で動物とともに時間を過ごす」のは、水族館飼育員ならではの特徴といえるでしょう。
さらには繁殖や出産、教育普及のためのイベント企画や解説も大切な仕事の一つです。水族館には多くの希少動物が飼育されていますので、繁殖、出産を通じて命をつないでいくこと、そしてその命の大切さや生態を伝えていくことは、水族館の使命です。
この他、水槽の水質管理や、潜水するための機材の点検などもあります。特に水がきれいかどうかは、水に生きる動物たちの健康を維持するためのいわば生命線であり、最も大切な事の一つです。水の循環システムが問題なく働いているかどうかや、水質に異常はないかは細心の注意を払って確認します。

東京動物専門学校の富里キャンパスでアシカトレーニングを行う学生
水族館飼育員以外にも様々な人が関わっている
水族館には、飼育員以外にも、獣医師、展示企画スタッフ、接客対応スタッフなどが働いています。獣医師は、館内の動物の診療や治療を行いますし、展示企画や接客対応スタッフは、水族館のイベント企画・広報、ショップ運営、お客様対応などを通じて施設全体を支えています。水族館で働くために必要な知識や技術
水族館で働くためには、特に水族館飼育員になるには、動物への深い愛情はもちろん、それを支える専門知識と技術の礎が必要です。水棲生物に関する知識
まず、動物全般、特に水棲生物に関する知識を持っていることは、働くうえで大きな武器になります。例えば、水棲生物の生態や、餌などの飼育管理の基礎、病気に関する知識などです。水棲生物の飼育に関する技術
技術面では、実際に動物を扱うスキルが重要です。具体的には、安全な餌やりの仕方や健康状態の確認方法、水槽の清掃にあたる器具の扱い方、イルカやアシカのショートレーニングなどの経験があることも、働くうえでの大きな支えになります。
潜水士資格が役に立つ
ちなみに、前述の通り、水に潜ることも仕事の一つですので、潜水士資格があると役に立ちます。さらに、ろ過槽やポンプなど設備の管理も仕事の一部ですので、機械の簡単なメンテナンス技術やトラブル対処能力があると心強いでしょう。水族館の仕事のやりがいと大変さ・きつい点
水族館の仕事は、命を預かる仕事と言えるほど、生きものと向き合う仕事です。その分大変な仕事であることは事実ですが、他では得られない大きなやりがいがあることもまた事実です。例えば、- 自分が世話をした動物が元気に育ったとき
- 日々の観察から動物たちを取り巻く社会や個性を発見したとき
- 長年取り組んできた繁殖が成功し新たな命が誕生したとき
- ショーで自分のサインやホイッスルによって動物と息を合わせてパフォーマンスができたとき
- 来館者の方々に喜んでもらえたとき
これらは、動物と深く関わる仕事ならではの感動です。また、小さな子どもが動物に興味を持つきっかけを作れたり、絶滅危惧種の保全に貢献できたり、社会的意義を感じられる場面が多いのも水族館飼育員ならではです。
水族館で働いた経験のある東京動物専門学校の卒業生に聞くと、こんなことを教えてくれました。
「どんな生きものが面白いと思ってもらえるか、どんな解説内容だったら興味をもってもらえるか、生きものの特徴が伝わる展示・解説はどんなものか・・・などを考え、実際にそれらに反応があったりすると嬉しかったですね。
イルミネーション感覚で水槽を見て、ただ「きれいだね」で終わらずに、「生きものについて学べて楽しかった」という反応を引き出すことに、やりがいを感じていました(魚類や無脊椎も含めると飼育種数がとても多く、その分幅広い知識が必要になることが大変でしたが 苦笑)。
ちなみに、一番難しかったのは、ヒトデやホヤ、サンゴといった「生きものに見えない生きもの」の解説でした。」
一方、「動物と毎日ふれあえる楽しい仕事」だけかというと、それだけではありません。水族館で働く上では、大変さやきつさもあります。たとえば、・・・・・・・。
ショーパフォーマンス動物の体調管理
ショーを行う上で、動物の健康状態が最も大切です。ベストの状態でなければショーは失敗します。動物は、その日の体調により動きが異なります。
ショーで使用する餌の分量も考えながら1日の給餌量を調整し、ショーの時間に合わせてベストコンディションに持っていきます。これはとても大変なことです。
精神的にタフな時も
動物は言葉を話しませんから、信頼関係を築くためには熱意と時間が必要です。担当する動物とのショーに失敗したり、トレーニングがうまくいかなかったりすることも少なくなく、そのたびにプレッシャーがかかります。
また、長年一緒に過ごしてきた動物が病気になったり、最悪の場合命を落としたりすることもあります。その度に悲しみや寂しさを感じますが、それでも動物たちのために、次のステップに進むのが飼育員です。
体力勝負
水族館飼育員の仕事は、体力勝負の面があります。重い水槽器材を運んだり、足元の滑りやすい場所を行ったり来たり、大量の餌の仕込みをしたり、、、、。手は傷ができやすく、特に冬はあかぎれなどに悩まされたりします。
また、ショートレーナーやイベント担当する場合は、泳ぎっぱなしの一日になることも珍しくはありません。特に冬の水中ショーは、氷水につかるようなものなのでそれだけでも大変ですが、同時にパフォーマンスのため笑顔で居続ける必要がありますので、簡単なことではありません。
魚をさばくことも仕事の一つ
餌の準備の際には魚をさばきますので、魚の生臭さや血を見ることにも慣れておいた方がいいでしょう。また、このおかげで一年中手は皸(あかぎれ)状態になります。体の大きなイルカは、食べる量が多いので準備も大変です。
勤務形態は不規則になることが多い
水族館はレクリエーション施設なので、土日祝日や大型連休・夏休みなどの学校の休業期間は繁忙期にあたります。従って、土日祝日休みといった勤務形態になることは難しく、基本的には一定期間ごとに事前に作成されたシフト制の下で働きます。
また、動物を24時間体制で見ていなければならないような場合には、宿直勤務になることもあるので、不規則な生活になる場合があることを予め分かっておくといいでしょう。
水族館で働くための競争率
競争率は高い
多くの水族館では、募集人数が少なく競争率が高い傾向があります。新設時には一挙に採用するものの、その後は欠員補充型となるからです。特に人気の大型水族館や公立水族館では、一度の採用試験に応募者が殺到しその門は広いとはいえません。
人によっては、希望する職場に就職できるまで、契約社員やアルバイトで経験を積むケースもあります。
しかし、情熱は壁を超える
しかし、そのような壁を超える情熱がある人にとっては、生涯のやりがいとなる素晴らしい仕事であることも間違いありません。実際に、水族館飼育員として働く卒業生の中には、こんな人がいます。
「水族館飼育員を目指していたものの希望就職先にはその求人がなかったため、はじめは接客部門で入社し、駐車場案内、チケット販売、インフォメーション、団体客対応など幅広い接客業務を担当していました。しかし、夢をあきらめずに熱意をもって取り組んだ結果、飼育部門への異動が決まり、今では日本でも数少ないベルーガのトレーナーとして働く事が出来ています。」

年に一度開かれる学校祭でのアシカショーの様子
憧れの水族館で働くにはどんな進路がある?
多くが大学・専門学校・短大に進んでいる
水族館で働く人の多くは、大学か専門学校に進んでいます。どちらがいいかというと、それぞれにメリットがあり、自分の目指す方向性や学びたい内容によって異なります。水棲哺乳類や鳥類か、魚類かで学ぶ先は変わってくる
イルカやアザラシといった水棲哺乳類やペンギン(鳥類)か、それとも魚類か、どちらの飼育を目指しているのかによって進学先の選択肢は変わってきます。大学と専門学校の違い
大学の場合 ~学術的な学びと資格~
大学に進学する場合、水族館での仕事に直結しやすい学部としては「水産学部」「海洋学部」「農学部(畜産系)」「理学部(生物学系)」などが挙げられます。大学に進むメリットは、学芸員資格や教員免許など将来選択肢を広げる資格取得が可能な点、そして研究活動を通じて専門性を磨ける点です。
一方で、実践的な飼育現場の経験は専門学校よりは少なくなります。
専門学校の場合 ~仕事に直結する実践的な学びと資格~
専門学校に進学する場合は、動物や海洋生物の飼育に特化したコースを持つ学校を選ぶことになります。専門学校のメリットは、なんといっても実践的なカリキュラムと就職サポートです。インターンシップ(施設研修)として、実際の水族館で職場体験を積める機会が充実していることも特徴です。
例えば、東京動物専門学校のように在学中から230種1500頭羽もの動物を飼育する学校では、授業内で動物の世話やトレーニングといった実践を通じて学ぶことができます。
実際、東京動物専門学校の富里キャンパスでは、カリフォルニアアシカやゴマフアザラシといった海獣類のトレーニング実習を行っており、在学中から海の哺乳類に直接触れて学ぶことができます。
また、東京動物専門学校の場合、2年次後期に約1ヶ月間、全国各地の動物園・水族館等で実習を行うカリキュラムが組まれています。
このように、専門学校は即戦力となる人材育成と就職支援に特化しているため、「早く現場に出て働きたい人」や「実習を通じてスキルを磨きたい人」に向いているでしょう。
結論としては、自分が何をどのように学びたいか。
結論としては、大学と専門学校のどちらが「有利」というより、自分がどういう形で学びたいか、将来どのように動物と関わっていきたいかかで選ぶのが良いでしょう。現場で役立つスキルを重視するなら専門学校、学術的な知見や資格取得も視野に入れるなら大学、といった具合ですが、いずれにせよ、水族館で働くには専門性が求められるため、高校卒業後に何らかの形で関連分野の勉強を続けることが「王道」といえます。
学校の選び方
オープンキャンパスを活用しよう
水族館で働く夢を叶えるためにどの学校で学ぶかという学校選びは、大学であれ、専門学校であれ、重要な選択ですが、自分に合った環境を選ぶことが大事です。その際に是非活用してほしいのが、オープンキャンパスです。
各学校の特色は公式サイトやSNSなどで詳しく知ることができますが、オープンキャンパスでは、その学校の施設見学や模擬授業体験、在校生・教員との座談会などが用意されており、資料請求だけでは分からない学校の雰囲気を味わうことができます。
特に複数校で迷っている場合は、現地で自分の肌で感じることが出来ます。
学校選びのポイント① カリキュラム内容
水族館で働くためのスキルは、教科書からの知識だけでなく、実習や現場経験から得る部分が大きいです。
なぜなら、動物相手の仕事は、実際に体を動かして対応することが大事だからです。
このことから、学校選びの際は、どのような実践的なカリキュラムが組まれているのかを調べてみるといいでしょう。
一般的には、専門学校では在学中から動物の世話に携わる機会が豊富に設けられ、大学ではフィールドワークや附属水族館での実習がカリキュラムに組み込まれています。
学校選びのポイント② 就職実績
またもう一つの学校選びのポイントは、就職実績です。目指す業界への就職者数が多い学校は、それだけ指導ノウハウやネットワークが蓄積されています。東京動物専門学校のカリキュラム内容と就職実績
たくさんの動物に囲まれて学ぶ
東京動物専門学校では、1年次から校内で様々な動物の実践的な飼育実習が行われています。犬猫はもちろんのこと、ホワイトタイガーやナマケモノ、アルパカ、カンガルー、バクといった動物園でしか見ることのできない動物たちや、鳥類爬虫類、そして水族館につながる海獣類(アシカやアザラシ)まで、230種1500頭羽を超える動物を学生がローテーションで担当し、餌やり・清掃・健康チェックなどを学びます。
教室で習った理論をすぐ実習で試せる環境が整っていて、動物への接し方や安全管理を、日々の実践の中で修得していきます。
2年次になると施設研修(インターンシップ)として、約1ヶ月間、希望する水族館や動物園で職場体験を行います。実際に職員の一員として飼育業務に携わり、リアルな現場体験を積むことができます。
先輩たちが開校以来35年積み重ねてきたネットワークのおかげで、研修先は全国どの水族館でも選ぶことができ、多くの施設が東京動物専門学校の学生を受け入れてくれています。

東京動物専門学校で飼育されるカリフォルニアアシカ(左)とゴマフアザラシ(右)
卒業生は延べ 3,500 人以上
現在までに卒業生が3,500名を超え、全国の動物園・水族館ほか様々な施設で活躍しています。
特に動物園や水族館に強く、 2024年3月卒業生にいたっては、46%が動物園や水族館に就職しています。
現在も、次のような全国の水族館で卒業生が活躍しています (2024年5月現在)。卒業生が多いということは、それだけ現場とのつながりも強い証拠です。オープンキャンパスではそうした卒業生の活躍についても紹介されることが多いので、ぜひチェックしてみてください。
| 葛西臨海水族館 | サンシャイン水族館 | しながわ水族館 | すみだ水族館 |
| よみうりランドアシカ館 | アクアパーク品川 | 箱根園水族館 | 横浜・八景島シーパラダイス |
| さいたま水族館 | 鴨川シーワールド | 青森県営浅虫水族館 | 鶴岡市立加茂水族館 |
| 仙台海の社水族館 | なかがわ水遊園 | 茨城県大洗水族館 | 上越市立水族博物館 |
| のとじま水族館 | 下田海中水族館 | 幼魚水族館 | 名古屋港水族館 |
| 鳥羽水族館 | 伊勢夫婦岩ふれあい水族館シーパラダイス | 道の駅紀宝町ウミガメ公園 | 琵琶湖博物館 |
| ニフレル | アドベンチャーワールド | 太地町立くじらの博物館 | 新屋島水族館 |
| しまね海洋館 | 長崎ペンギン水族館 | 大分マリーンパレス水族館「うみたまご」 | おきなわワールド |
| 沖縄美ら海水族館 |
夢に向け今からできる準備
動物に関する知識を身につけよう ~生物~
前述の通り、水族館で働くには動物に関する知識が必要です。では具体的には、どんな科目や分野を勉強しておくといいでしょうか。まず高校までの段階で言えば「生物」です。水族館では、ペンギンやカワウソなど哺乳類・鳥類だけでなく、魚も飼育していますし、クラゲやサンゴといった無脊椎動物も扱います。
様々な動物の分類や生態、生理機能について興味を持って知識を蓄えておくと、大きな支えになるでしょう。
水質に関する知識も大切 ~化学~
次に「化学」も学んでおくといいですね。
水族館の飼育員は毎日水質検査を行い、水温やpH(いわゆる酸性よりかアルカリ性よりか)か、塩分濃度、アンモニアや亜硝酸の濃度などをチェック、動物たちが生息する水環境が野生環境と同じかどうかを確認します。
これは、生息場所の化学的な性質を理解していないとできない仕事です。水に生きる生きものにとって適切な水質を維持することは、とても大切なことの一つですし、理解しておくとよいでしょう。
足を運んで動物や仕事を知ろう
「百聞は一見に如かず」。
ぜひ時間を見つけて、水族館の現場を体験してほしいと思います。
最近では、多くの水族館でバックヤードツアーや飼育体験イベントを開催しています。飼育員の仕事を間近で見たり、エサやり体験ができる企画もあるようです。
また、学校選びのところでもお話ししましたが、興味のある専門学校や大学のオープンキャンパスに足を運ぶのもおすすめです。東京動物専門学校でもオープンキャンパスや体験入学を随時開催しており、在校生や講師から直接話を聞いたり実習体験をすることができます。学校の雰囲気やカリキュラムを知る良い機会です。
いかがでしたでしょうか。水族館で働くこと、また働くための学校選びなどのポイントについてお話しました。
「好き」という気持ちを大切にしてしっかりと準備をすれば、きっと憧れの職業に近づけるはずです。興味を持った方は、ぜひ一度、大学や専門学校のオープンキャンパスに参加してみましょう。
尚、東京動物専門学校のオープンキャンパスでは、水族館にいる動物に限らず、ホワイトタイガーなどの普段見ることのできない動物を間近に見ながら飼育体験ができたり、在校生が日頃どんな勉強をしているか、直接話しを聞けたりします。
実際に動物たちに触れたり先輩の話を聞いたりすることで、進路のイメージが一層具体的になるはずです。高校1年生や2年生でも参加できますので、ぜひ早いうちに学校に足を運んでみてください。
水族館で働くという夢は、正しい努力を積み重ねれば、必ず実現できると信じています。
東京動物専門学校では、動物とともに働く未来を目指すあなたを、全力でサポートします。

次回は、水族館で働きたい皆さんに向けて「水族館の飼育員になるには?待遇・資格・学校の選び方」を徹底解説したいと思います。
お楽しみに!
執筆者:川原 祥孝<学生課所属、飼育所(実習施設)副長>
 |
保有資格 | 薬剤師、愛玩動物看護師、潜水士、二級ボイラー技士、玉掛け技能者、小型移動式クレーン運転技能者 |
| 自己紹介 | 休日は、家族と過ごすことが好きです。特に外出が好きですが、訪問先でも仕事に使えそうな事を探してしまい家族に怒られることもあったり。仕事をする上で大切にしているのは、「学生が困難な夢に挑戦している時、適度な距離感を保ちながらしっかりサポートすること」です。学生の自主性を尊重しながら、よりよいサポーターでいられたらと思っています。最近はまっている趣味は投資で、企業を調べて、考え方に共感できた企業に投資しています。 |


